ハムスター飼育を行っている際にトラブルは付きものです。特に飼育を始めたばかりの方は注意点を知らないために大きな事故につながる失敗をしてしまう可能性があります。
例えば、ハムスターの生死に関わる事故として、高い場所からの落下があります。人が立ち上がった状態でハムスターを持ったり、高い場所にケージを設置している場合に驚いたハムスターが急に走り出すことがあり、悲惨な事故は後を絶ちません。
このページでは、ハムスターを高い場所から落下させてしまった人のために、どんな危険があるのか、ハムスターを死なせないための対処法などを紹介します。
ハムスターの落下について

インターネット上で検索すると、ハムスターを高い場所から落下させてしまい心配している方、死なせてしまった方の投稿が多数見受けられます。飼い主の中にはハムスターを高い位置で飼育している方や立ち上がった状態で手に乗せる人もいて、ハムスターを落下させてしまう事故が後をたちません。
ハムスターが非常に高い位置から落下してしまうのには、ハムスターも視力が悪く高さを認識できていない、生存本能のために逃げることを最優先にしているなどの理由があります。
飼育に慣れている方は、ハムスターを高い場所に持っていかないよう気をつけます。しかし、仮に落下してしまった場合どのような問題があるのか確認してみましょう。
ハムスターの落下の危険
ハムスターが高い場所から落下した際には、様々な危険が考えられます。以下の4つは頻繁に報告されている怪我になります。
- 骨折
- 脳震盪
- 内臓へのダメージ
- 死
ハムスターをフローリングなど硬めの床に落下させてしまうと、着地時に手足の骨を痛める可能性があります。ハムスターは体が軽いため骨への負荷は小さいのですが、骨自体が非常に細いため、綺麗に着地したように見えても折れている可能性があります。
また、腹部や頭部から落下した場合には、内臓や脳にダメージを受けることがあります。一見、元気に動いているように見えても体内では回復不可能なダメージを受けているので早急な対処が必要です。
一般に落下の危険性は高さに比例し、高ければ高いほど死の確立が上がります。ただし、低い位置から落下したとしても着地する部位が悪かったり床が硬いとハムスターの生死に関わります。
落下後の対処法
ハムスターを高い位置から落下させてしまうと、死なせてしまう可能性が非常に高くなります。このような事故が起こった際の対処法を確認しておきましょう。
- よく観察する
- 病院に連れて行く
- 事故の原因を取り除く
よく観察する
ハムスターを落下させてしまった場合には、まずは様子を見ましょう。ハムスターが逃げないようであれば、手足に異常がないか確認します。
落下したハムスターが手足を引きずって歩いていたりまっすぐ歩けなくなっている場合には、身体もしくは脳にダメージを受けています。また、落下した場所や逃げた先で生きたまま動かなくなっている場合には内臓に大きなダメージを受けている可能性が高いです。
これらの場合、自然に回復するケースも見られますが、時間の経過と共に弱って死んでしまうこともあります。
病院に連れて行く
ハムスターに異常が見られなくてもすぐに病院に連れて行くようにしましょう。ハムスターを含め、多くの小動物は弱っている姿を見せることで、敵に襲われてしまいます。そのため、死のギリギリまで怪我や病気を隠す癖があります。
ハムスターの様子が変わった頃には既に手遅れで、病院に連れていく前に死んでしまうということが多々あります。落下後には異変が見られなかったとしても念には念を入れて病院に連れて行くことが大切です。
事故の原因を取り除く
病院を受診したら同じ事故が起こらないよう飼育環境を見直したりハムスターとの触れ合い方を変えるようにしましょう。高い位置にハムスターケージを置いている場合は、刑事を開けた際にハムスターが飛び出て落下する可能性があるため床など低い場所に置き換えましょう。
また、ハムスターに触る際には必ず座る、高い位置に登れないよう物を置かないなど心がけることが大切です。ハムスターに部屋んぽをさせている方には、専用のサークルがおすすめです。危険な場所に入ったり登る可能性がなくなるため安心感があります。
ハムスターの部屋んぽについてはこちらの記事をご覧ください。

病院の受診をしてください
このページでは、ハムスターの落下についてその理由や対処法を紹介してきました。落下によってハムスターが受けるダメージの大きさや種類は、条件によって大きく異なります。
骨折、脳震盪、内臓へのダメージ、死など怪我の種類は様々ですが、大切なことは落下した後にしっかりと対処することです。
インターネット上で様々な情報を集めることもできますが、1件1件の事例について詳しく調べる事はできません。ハムスターを死なせたくない場合には、動物病院など専用の受信期間を利用して詳しい診察と適切な処置を受けさせましょう。
このページでも記載しましたが、多くの小動物は死のギリギリまで怪我や病気を隠します。大切なのは症状が現れる前に病院を受診することです。

病院探しが大変だったりお金がかかることもありますが、大切なペットの命を守ってください。
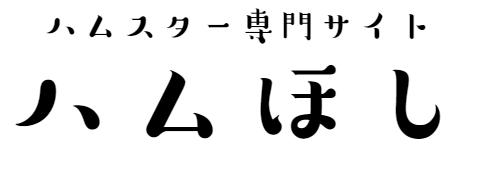




是非コメントを残していってください!
今、ハムスターが落下しました、
後ろ足をぶつけました、
通常通り動いていますが、
死なないでしょうか、大丈夫でしょうか
コメントありがとうございます。
記事にもありますが、インターネット上の情報では一件一件の事例に対応することはできません。
高さがそれほどなければ怪我をしている可能性は低いですが、心配であれば動物病院の受診がおすすめです。
その際にはハムスターなど小動物を扱っているか確認してから行くと、対応してもらえないといったトラブル防止になります。
ぜひ役立ててください!
ハムスターを落下させてしまいました。鼻血が出てしまいました。一応止血はできました。今日はもう夜なので病院へ連れて行くことが不可能で困っています。朝起きたらパタリと死んでしまっているのではないかと考えるたびに涙が溢れてきます。どうすればよいですか?
ハムスターを30cmほど上から硬い床に落としてしまいました、、
その際右側から落ちてしまいゴンッという音がしました。
すぐに動き出して見た目は大丈夫そうなんですがほんの微かに右側を庇っているようにも見えます。
内臓とかがダメージを受けているのでしょうか?
また病院に行ける日も行く時間もなくてなるべく自分で解決したいです。
コメントありがとうございます。
30cmほどの高さであれば、怪我や致命傷に至る可能性は低いです。
ただ、硬い床とのことで衝突した箇所によっては心配が残ります。
今後数日間はハムちゃんの様子を見て、体を庇う様子が治るか、悪化していないか細かく確認してあげてください。
顔を打ってしまった場合、応急処置の方法は変わってきますか?今は家に居て、元気なんですけど…種類はゴールデンで、机に頭から机に落ちてしまいました。一応時間が経過して行動が異常だったらまた聞きますが、精神面などの心配もあるのでしょうか…もしあったらメンタルケアの方法も教えて欲しいです。
コメントありがとうございます。
顔から落下したとのことですが、高さがなければ怪我やストレスになる可能性は低いと思われます。
応急処置の方法も特段変わりはありません。
ジャンガリアンの3歳近い子が、50cmほど落下してしまいました。
床はフローリングで、軽いのに落下時にコンッとなりました。
左目が衝撃で突出してしまい、眼球自体が赤く腫れ上がって目を閉じれないようです。
深夜なので、明日朝一で病院に連れて行きます、、、。
コメントありがとうございます。
その後の経過はいかがでしょうか?
ジャンガリアンの生後1ヶ月半の子です。手の上に乗ってもらっておやつを渡した後すぐにケージの中に戻したのですが、その際3cm程の高さから勢いよく飛び降りてしまいました。その後4時間後ぐらいにケージを見ると歩き方がおかしくなっていて、右手が常に上に上がっている状態でした。毛繕いするのも少しやりづらそうです。ですが全く動かない訳ではなく何かに登る時は両手を使っているように見えます。ハムスターの掌は左手は完全に開いているのですが、右手は閉じているような状態です。このまま様子を見ておいて大丈夫でしょうか。
コメントありがとうございます。
3センチ程度の高さであれば怪我をするのは稀ですが、生後間もない事や歩き方がおかしい事を踏まえると骨折の可能性も考えられます。
骨折により即死というケースは少ないですが、治療が遅れるとハムちゃんが長期間痛みを感じるうえ、今後の生活に支障をきたします。
今日、明日ほど様子を見て手をかばうように歩いていたり痛みを感じているようでしたら早めに病院を受診してあげてください。
様子見ようと思います。
ご返信ありがとうございます!
先程うちのハムスターが全部合わせて30cm程の高さから、枕から布団、布団から壁に当たる際に頭と背中をぶつけて、そのまま床に落ちてしまいました。
落ちたあとに少しびっくりしてこちらを見上げていたのですが、その後歩かせてみたところ、ちゃんとまっすぐ、ふらつくことなく歩いたり、走ったりしていました。小屋に戻したら落ち着かないようで、10分くらいずっと毛づくろいをしていました。明日になって死んだり、ふらふらしたりしていないかとても心配です。大丈夫でしょうか?
ちなみに、ハムスターは2歳8ヶ月です。
よろしくお願いします
コメントありがとうございます。
その後ハムちゃんはお元気でしょうか?
30センチほどの高さで、直接床に落ちた訳ではないようですので怪我の恐れは少ないと思います。
現在の状況をお教え頂ければと思います。
ハムスターを手に乗せていた時に誤って手を振ってしまい、30cm弱のところから落としてしまいました。失禁、出血、歩き方の異変などは見られません。回し車もやっていました。明日の朝病院に行こうと思っていますが、今私ができることはありますか?また、診療代でいくらくらい必要になりますか?
コメントが遅れてしまい申し訳ございません。
30センチ程であれば怪我の可能性は低いと思われます。
病院からのアドバイスなどありましたらぜひお聞かせください。
ハムスターを35cm位の棚から落ちました。背中側から落ちました大丈夫ですか?
今日、ハムスターを机の上にのせていたら落下してしまいました。(70㎝くらいの高さ)背中から落ちて、特に足を引きずったりということは無いのですがとても不安です。どうしたら良いでしょう?
シャンガリアンハムスターです。
ハムスターを35cm位の棚から落ちました。背中側から落ちました大丈夫ですか?
初めまして。長文失礼いたします。
ハムスターが50センチほどの高さから落下しました。
翌日、動きがスローモーションのようになっていたので慌てて病院に連れて行きました。
脳にダメージがあるかもしれないとの事でしたので触らず様子を見ていました。
次の日は夜20時頃に起きてきて、あくびを2回ほどした後1時間〜2時間の間にあくびを10回ほどしています。
これも脳へのダメージが原因なのでしょうか?
また、脳へのダメージは時間と共に回復するものなのでしょうか?
動きはだいぶスムーズになってきてはいます。色々調べてみましたが分からなかったのでお教え頂ければ幸いです。
ハムスターを約40㎝ほどの高さから落としてしまいました。
その後は、いつも通り走ったり、足を引きずっている等、おかしな様子は見られません。
大丈夫でしょうか?
ジャンガリアンハムスター(生後4ヶ月)を30㎝ぐらい高さから硬い床に落としてしましました。這いつくばって落ちてその後30秒ぐらい動かなかったです。でも,すぐに小屋に帰ってピーナッツを食べ始めました。がこれは大丈夫なのでしょうか?
生後1ヶ月のハムスターが70センチぐらいから落ちてしまって背中を打ちましたでもあっても音はしませんゲージに戻しても大丈夫そうだったんですけどどうしたらいいですか?
ハムほしの返信待ちです
ハムほしの返信待ちです
返信お願い致します
飼っているハムスターを、何センチかわからないんですけど、落下させてしまいました。元気そうなんですけど、少しぐったりしています。とても心配です。どうすれば良いのでしょうか?返信お願いします。
うちの飼ってるハムスターが、お風呂の上によじ登って間に挟まるんですけど何なんですか?教えて下さい!返信待ってます!